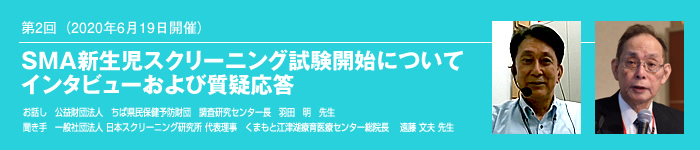
Q1
産科医のSMA新生児スクリーニングに対する理解度はどのくらいしたか?(疾患や検査について、どの程度の説明が必要でしたか?)
産科医のSMA新生児スクリーニングに対する理解度はどのくらいしたか?(疾患や検査について、どの程度の説明が必要でしたか?)
羽田 思ったよりも良好でした。とくにヌシネルセン、ゾルゲンスマといった高い薬価の話題があったので、ある意味、情報は周知されていました。SMAという疾患のことがわかっていたのかもしれません。一刻も早い治療が必要で、それには新生児スクリーニングが必要だということが、その重要性としてしみわたっていたと思います。
Q2
どのような手順で展開しましたか?例えば産科への説明の方法についてなど教えてください。
どのような手順で展開しましたか?例えば産科への説明の方法についてなど教えてください。
羽田 遠藤先生から、この件の話があったのが2019年12月でした。
まず、千葉大学大学院医学研究院生殖医学講座教授の生水真紀夫先生に、ご理解とご支援をいただきたく、小児科の先生にも同時に説明に行きました。 そこで、千葉県産婦人科医会に説明する機会をつくっていただきました。私たちも産婦人科医会に周知する手順が必要だと認識していました。
千葉県産婦人科医会理事会が2020年1月に、また、同学術集会が2月に予定されていました。
手順としては、理事会は私が、学術集会は帝京平成大学教授の高柳正樹先生がSMAの新生児スクリーニングの重要性をご説明にうかがいました。理事会では質疑応答を含め30分間位お時間をいただき説明しました。
内容に関する質疑は「産科として手間がどの程度かかるか知りたい」というようなものが中心でした。 具体的に下記のようなことについて説明しました。
まず、千葉大学大学院医学研究院生殖医学講座教授の生水真紀夫先生に、ご理解とご支援をいただきたく、小児科の先生にも同時に説明に行きました。 そこで、千葉県産婦人科医会に説明する機会をつくっていただきました。私たちも産婦人科医会に周知する手順が必要だと認識していました。
千葉県産婦人科医会理事会が2020年1月に、また、同学術集会が2月に予定されていました。
手順としては、理事会は私が、学術集会は帝京平成大学教授の高柳正樹先生がSMAの新生児スクリーニングの重要性をご説明にうかがいました。理事会では質疑応答を含め30分間位お時間をいただき説明しました。
内容に関する質疑は「産科として手間がどの程度かかるか知りたい」というようなものが中心でした。 具体的に下記のようなことについて説明しました。
- ろ紙について:今までと同じろ紙を使える可能性があり、新たな採血は必要ない(この時は、千葉県と千葉市の行政に、タンデムマスと同じろ紙を使えるようにお願いをしていました)。
- インフォームド・コンセント:受諾が必要なので、その手間はかかる。
- 説明資料について:パンフレットなどを作成し提供するので、手間がかからないように進める。
その結果、おおむね好意的に受け入れられて、理事会の方でも参加してもいいという意見となりました。
産科の先生で協力したいと申し出がある施設にはどんどん、話を進めました。
当初は、産婦人科すべを1病院ずつ訪問して説明しないとならないかと思っていたのですが、周知されたようです。詳細な質問については、その後電話により、ちば県民保健予防財団で対応していきました。その後は特に問題は起きていません。
インフォームド・コンセントのところでサインをもらう必要がありますが、今までの新生児スクリーニングでやってきたという背景があるから周知はスムーズでした。
産科の先生で協力したいと申し出がある施設にはどんどん、話を進めました。
当初は、産婦人科すべを1病院ずつ訪問して説明しないとならないかと思っていたのですが、周知されたようです。詳細な質問については、その後電話により、ちば県民保健予防財団で対応していきました。その後は特に問題は起きていません。
インフォームド・コンセントのところでサインをもらう必要がありますが、今までの新生児スクリーニングでやってきたという背景があるから周知はスムーズでした。
Q3
千葉県は広く、自治体も広範囲にわたります。 そういった点で産科に周知することの難しさはありましたか?
千葉県は広く、自治体も広範囲にわたります。 そういった点で産科に周知することの難しさはありましたか?
羽田 正直あまり苦労はありませんでした。環境省で2011年より実施した、10万組の子どもたちとそのご両親に参加していただく大規模な疫学調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」では、結構ハードルが高かったのですが。今回はそのようなことはありませんでした。
Q4
実際には産科の病院の医療関係者が採血をすることになるわけですが、何か質問とかありましたか?
実際には産科の病院の医療関係者が採血をすることになるわけですが、何か質問とかありましたか?
羽田 質問は恒常的にあります。これはすべて、ちば県民保健予防財団で受け取って、QAを作成しファイルを作成保有し、また検査室のスタッフととも共有するようにしています。そうした対応に関しては、派遣スタッフを1人雇用し、それ以外のスタッフは財団の調査研究センターの2-3人が対応。検査室では検査部長、パンチアウトを行う検査技師に対応してもらっています。
インフォームド・コンセントを受諾した方だけを検査するため、バーコードを利用していますが、このバーコードの照合は派遣スタッフにお願いしています。
インフォームド・コンセントを受諾した方だけを検査するため、バーコードを利用していますが、このバーコードの照合は派遣スタッフにお願いしています。
Q5
妊婦さんやご家族からの(直接的または間接的な)問い合わせはどのようなものがありましたか?
妊婦さんやご家族からの(直接的または間接的な)問い合わせはどのようなものがありましたか?
羽田 それがほとんどありませんでした。ひとつ、クリニックを通して、里帰り出産の場合、どう対応すればいいかという問い合わせはありました。その場合、もし陽性の場合は、一旦千葉こども病院を受診してもらい、それから地元の病院に連絡して、対応するという方法がとられています。他には今のところありません。
Q6
千葉市や(その市町村)と県での説明はどのように行いましたか?
千葉市や(その市町村)と県での説明はどのように行いましたか?
羽田 千葉市と千葉県は別々な行政単位ですが、今までの新生児スクリーニングでもいっしょにやってきた体制や経緯があります。千葉県に私と高柳 正樹先生、村山 圭先生の3人で、2019年の早い時期に説明にうかがった時も、千葉市の担当者がいらしていて、説明は一回で済みました。
実際の許可は千葉市と千葉県と2つからもらうことになりますが、その点ではあまり苦労はありませんでした。とにかく行政に早く説明に行くことが大切で、それがスムーズに進まないと、その後の医療機関の負担が増えることになります。
実際の許可は千葉市と千葉県と2つからもらうことになりますが、その点ではあまり苦労はありませんでした。とにかく行政に早く説明に行くことが大切で、それがスムーズに進まないと、その後の医療機関の負担が増えることになります。
Q7
貴財団での業務で新規立ち上げなどにご苦労された点はどのようなところですか?
貴財団での業務で新規立ち上げなどにご苦労された点はどのようなところですか?
羽田 今までの事業の立ち上げと比べても、今回のSMAの新生児スクリーニングの立ち上げは、とにかく時間がありませんでした。「こんなにバタバタやってうまくいくのか?」という意見が多かったわけです。とにかく大変でした。
検査の現場では、不可能ですという意見が大半で、当初は行政のろ紙を使えないことになっていたわけですから、それらを一つ一つ解決していく対応に追われました。
行政に説明に行き、千葉県産婦人科医会に説明に行ったのは2020年1月頃です。
検査を一からやるのはハードルが高いため、難病の解析や遺伝子研究をこれまでも共同して行ってきた公益財団法人 かずさDNA研究所にSMA検査の可能性を打診し、検査手法を含め、共同で実現に向けて取り組もうということになりました。
行政に説明に行き、千葉県産婦人科医会に説明に行ったのは2020年1月頃です。
検査を一からやるのはハードルが高いため、難病の解析や遺伝子研究をこれまでも共同して行ってきた公益財団法人 かずさDNA研究所にSMA検査の可能性を打診し、検査手法を含め、共同で実現に向けて取り組もうということになりました。
Q8
窓口対応はちば県民保健予防財団調査研究センターで行うと聞きましたが、その後の実際にろ紙が届いてからの業務はどのような流れですか?
窓口対応はちば県民保健予防財団調査研究センターで行うと聞きましたが、その後の実際にろ紙が届いてからの業務はどのような流れですか?
羽田 ろ紙のパンチアウトなどの作業は、従来の検査後、つまりタンデムマスの後に行うという流れです。
次に、名簿などのシステムから必要な情報をどうやって引き抜くか、つまり、SMA新生児スクリーニングに参加するインフォームド・コンセントを受諾した人がどの方で、そのろ紙はどれなのか、ろ紙の照合作業を行う必要があります。これはかずさDNA研究所の細川先生がソフトを作ってくださって何とか間に合わすことができました。あと、コロナの影響などで発注した検査機器が予定通り来ないということもありましたが、ぎりぎりの検査体制で5月の連休明けに開始することができました。
Q9
検査のスピードという点を重視されていますが、その点で腐心されたことや工夫されたことはありますか?
検査のスピードという点を重視されていますが、その点で腐心されたことや工夫されたことはありますか?
羽田 血液ろ紙が届いてからの手順は以下の通りとしました。
- バーコードでインフォームド・コンセントを承諾した人を抜き出す作業をろ紙の届いた日に行う。
- パンチアウトは翌日、検査技師が行う。
- コントロールろ紙をいれて宅配便で発送。こうした作業で土日を挟むなどがあり数日かかります。
- かずさDNA研究所は当初1週間としていましたが、数日で結果を返却してくれます。 非常に速く、先天代謝異常疾患の報告より速い場合もあります。
Q10
当初採血から2週間以内に結果報告としていましたが、達成できているわけですね?かずさDNA研究所でのご苦労されている点は?
当初採血から2週間以内に結果報告としていましたが、達成できているわけですね?かずさDNA研究所でのご苦労されている点は?
羽田 達成できる場合と週末が入りできない場合があります。それとかずさDNA研究所が注文した検査機器が未だにきていないという事情もあります。
SMAの遺伝子検査は、まず、ロボットでろ紙からDNAを抽出する作業を自動化します。そしてその一部をとって定量PCRを行うという作業があります。 DNAを抽出するロボットは近々納品されますが、定量PCRの機械はまだ未定で、現在稼働できる機械は1台だけというのが現状です。そういう現状でがんばってもらっています。
SMAの遺伝子検査は、まず、ロボットでろ紙からDNAを抽出する作業を自動化します。そしてその一部をとって定量PCRを行うという作業があります。 DNAを抽出するロボットは近々納品されますが、定量PCRの機械はまだ未定で、現在稼働できる機械は1台だけというのが現状です。そういう現状でがんばってもらっています。
Q11
ろ紙にバーコードを付けていますが、これはいつ付けていますか?従来のスクリーニングではバーコード導入の重要性は指摘されていましたが、いままで実践はされていませんでした。
ろ紙にバーコードを付けていますが、これはいつ付けていますか?従来のスクリーニングではバーコード導入の重要性は指摘されていましたが、いままで実践はされていませんでした。
羽田 バーコードのセットをあらかじめ、産科に送っています。そして、インフォームド・コンセントの受諾の書類と採血したろ紙に張ってもらい、返送してもらいます。これは新しい取り組みといえます。その作業は産科の負担となります。
Q12
SMAスクリーニング検査は遺伝子検査ですが、産科や保護者から懸念とか質問はありましたか?
SMAスクリーニング検査は遺伝子検査ですが、産科や保護者から懸念とか質問はありましたか?
羽田 基本的にはありませんでした。診療に適した遺伝学的検査という理解は浸透しているようです。もちろん、SMAの遺伝子検査についての説明はパンフレット等には掲載しています。
Q13
SMAスクリーニング検査については、遺伝子医学と遺伝子倫理の専門家のトップのおひとりである羽田先生が日本で最初に倫理委員会を通したということになりますが、苦心したことなどはありますか?
SMAスクリーニング検査については、遺伝子医学と遺伝子倫理の専門家のトップのおひとりである羽田先生が日本で最初に倫理委員会を通したということになりますが、苦心したことなどはありますか?
羽田 そういうことになりますね。遺伝子解析を伴う研究倫理審査では個人情報保護法の考えを取り入れた改訂後、混乱することも多かったと思います。今回は、専門家も入れてきちんと通してきました。
それと倫理審査委員会での承認はまず、ちば県民保健予防財団で通しました。 倫理委員長が私で、申請者も私なので、私以外の先生が倫理委員会で審査して通したという経緯があります。その後、千葉県こども病院とかずさDNA研究所で、それぞれ倫理委員会の審査・承諾をとり、現在、高柳正樹先生のところで審査中という状況です。(インタビュー後、承諾済み)
それと倫理審査委員会での承認はまず、ちば県民保健予防財団で通しました。 倫理委員長が私で、申請者も私なので、私以外の先生が倫理委員会で審査して通したという経緯があります。その後、千葉県こども病院とかずさDNA研究所で、それぞれ倫理委員会の審査・承諾をとり、現在、高柳正樹先生のところで審査中という状況です。(インタビュー後、承諾済み)
Q14
日本で今後、SMAスクリーニングを広げていくときに、 羽田先生の作成された倫理審査書類はプロトタイプ的な存在なので非常に重要だと思います。そういう意味でこの「千葉モデル」は倫理面でも今後の普及についても意義が大きいと思いますが、これを今後のために公表することはできますか?
日本で今後、SMAスクリーニングを広げていくときに、 羽田先生の作成された倫理審査書類はプロトタイプ的な存在なので非常に重要だと思います。そういう意味でこの「千葉モデル」は倫理面でも今後の普及についても意義が大きいと思いますが、これを今後のために公表することはできますか?
羽田 もちろん可能です。私が千葉大学の生命倫理審査委員長だった時の申請書類に準じて、詳細な倫理審査書類のフォーマットを作りました。そうした依頼が遠藤先生や私のところにあれば、他の自治体でも利用できると思います。
Q15
千葉モデルを全国に普及する場合の重要なポイントは何でしょうか?
千葉モデルを全国に普及する場合の重要なポイントは何でしょうか?
羽田 とにかく最初に自治体の協力を得ることが最大で、まずはここに一番注力してください。
それと、検査の難易度が高いことです。コントロールろ紙を用意するとか、厳密にする必要があります。定量PCR検査は微妙な検査であり、自信満々となるには相当な技術を要するわけです。
例えばインバリッドといって、コントロールのDNAが少ないと正常といえない場合が出てきます。その場合、元のろ紙をもう一度パンチアウトしたり、だめなら再採血などが必要となります。慎重を要するわけです。あと、公費負担にする流れをどう作るかということもあります。
それと、検査の難易度が高いことです。コントロールろ紙を用意するとか、厳密にする必要があります。定量PCR検査は微妙な検査であり、自信満々となるには相当な技術を要するわけです。
例えばインバリッドといって、コントロールのDNAが少ないと正常といえない場合が出てきます。その場合、元のろ紙をもう一度パンチアウトしたり、だめなら再採血などが必要となります。慎重を要するわけです。あと、公費負担にする流れをどう作るかということもあります。
Q16
今後の課題としての公費負担についてどうお考えですか?兵庫や熊本ではSMA検査は有償でやるといった話もあります。例えば、3000円位でできるかという話もあります。実際に導入すると意外に抵抗なくできる場合もあるようです。
今後の課題としての公費負担についてどうお考えですか?兵庫や熊本ではSMA検査は有償でやるといった話もあります。例えば、3000円位でできるかという話もあります。実際に導入すると意外に抵抗なくできる場合もあるようです。
羽田 いきなり全額公費負担とならない場合は、どの位の費用負担をお願いするか。他の自治体もどの位の金額でできるかを考えていく必要があります。また、実際に費用を病院に請求する場合、事務作業が増えるわけで、事務スタッフが必要となる可能性もあります。
そうした場合、妊婦さんから電子マネーで決済できるかなど、容易にできるシステムが必要です。ただし、お産の費用と別として払うのは抵抗があるかもしれません。また、検査をするかどうかという判断が遅れたり、入金のやり取りを確認して検査になると 時間がかかることになります。その場合、急ぐ必要があるSMA検査とのタイミングがあわなくなることも考えられます。迅速な検査が必要な場合の障害にならないような方法が必要となります。今後の課題だと思います。
そうした場合、妊婦さんから電子マネーで決済できるかなど、容易にできるシステムが必要です。ただし、お産の費用と別として払うのは抵抗があるかもしれません。また、検査をするかどうかという判断が遅れたり、入金のやり取りを確認して検査になると 時間がかかることになります。その場合、急ぐ必要があるSMA検査とのタイミングがあわなくなることも考えられます。迅速な検査が必要な場合の障害にならないような方法が必要となります。今後の課題だと思います。